どうも、『てったのぶろぐ』管理人です。
秋ですね。
食欲の秋、収穫の秋なんて言葉どおり、この季節、たくさんの野菜をおすそ分けしてもらえる人もいるかと思います。
かくゆう私もその一人です。
そう、収穫されたなすをたくさんもらったのですよ。
ナス、おいしいですよね~。
筆者はお酒大好きなので、ナスはとても良い肴です。
今回はナスの魅力を伝えたく、ブログにしたためました。
1. ナスとは?
ナス(茄子、茄、ナスビ、学名:Solanum melongena)は、ナス科ナス属の植物。別名ナスビともよばれる。インド原産で、淡色野菜として世界中で栽培されている。果実は黒紫色が多いが、色や形は様々で多数の品種がある。
クセのない味わいと火を通したときのなめらかな食感が特徴で、品種によって様々な調理法があり、料理のジャンルを問わず使えるため、定番の野菜として欠かさないものとなっている。
出典:ナス/Wikipedia
『様々な調理法があり、料理のジャンルを問わず使える』
そう、ナスは便利なのだ。
2. 大量にもらったら冷凍保存
筆者が住んでるところは田舎です。
農家もいれば、家庭菜園で育てている人もたくさん。
知り合いに比例して、お裾分けも増えます。
あまりの多さに友人知人・親族にくばろうとしました。
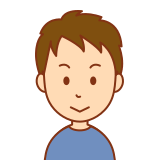
いらんいらん、うちも困ってんねや。
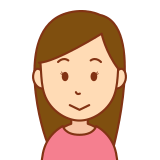
うちも、お裾分けしてもらってるわー。
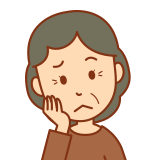
あら、あたしもあんたにあげようと思ってたのに〜。
ということでムリです。
ひとまず、あきらめて冷凍にしましょう。
■手順
- ナスのヘタを取り、”乱切り”か”輪切り”にする
- ジップロックに入れる
- 冷凍庫にIN

以上です。
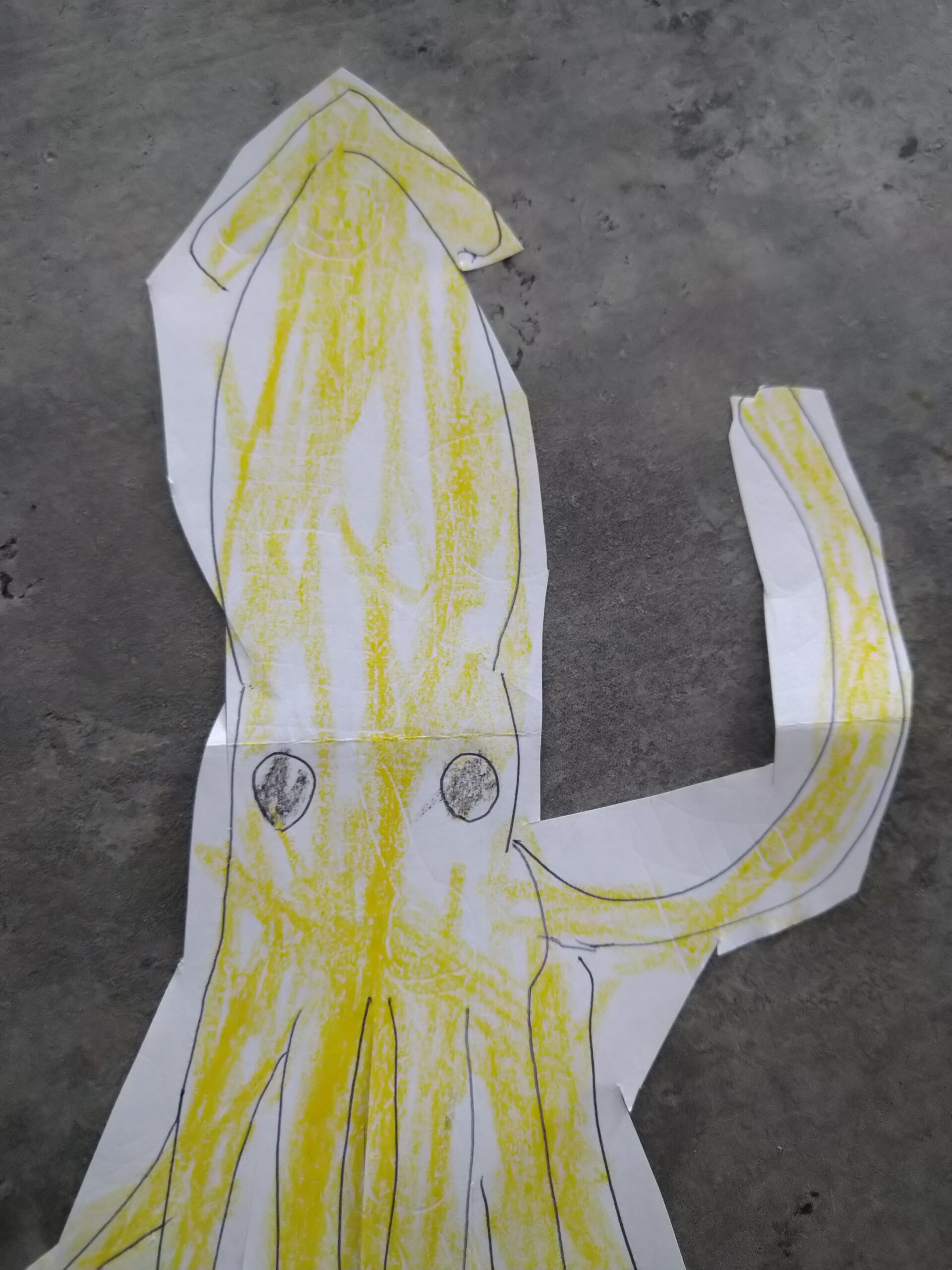
使いたいときに“凍ったまま”調理できるから便利だよぉ〜。
3. ナスの南蛮びたしでつくりおき
■材料・調味料
- ナス・・・容器に入る分
- めんつゆ・・・適量
- しょうがチューブ・・・適量
■手順
- ナスはヘタを取って輪切りに
(大きければ半月切りに) - ナスを素揚げするか、焼く
(今回は大量なので焼いてます) - フタつきの保存容器に”しょうがチューブを混ぜためんつゆ”を投入
- ナスがひたひたになるようにつけましょう
- 冷蔵庫にIN。
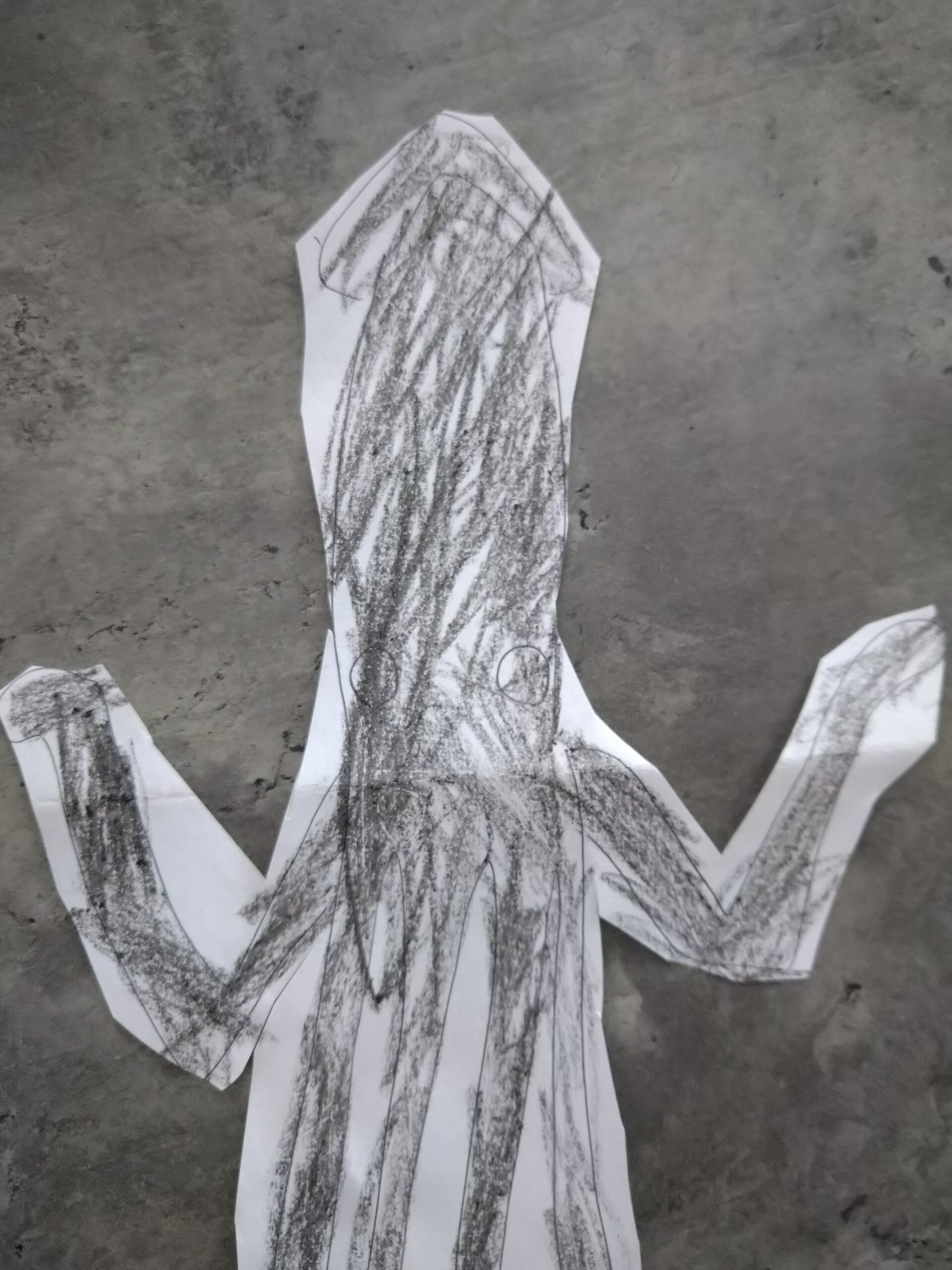
フタのできる容器を使うといいよ。
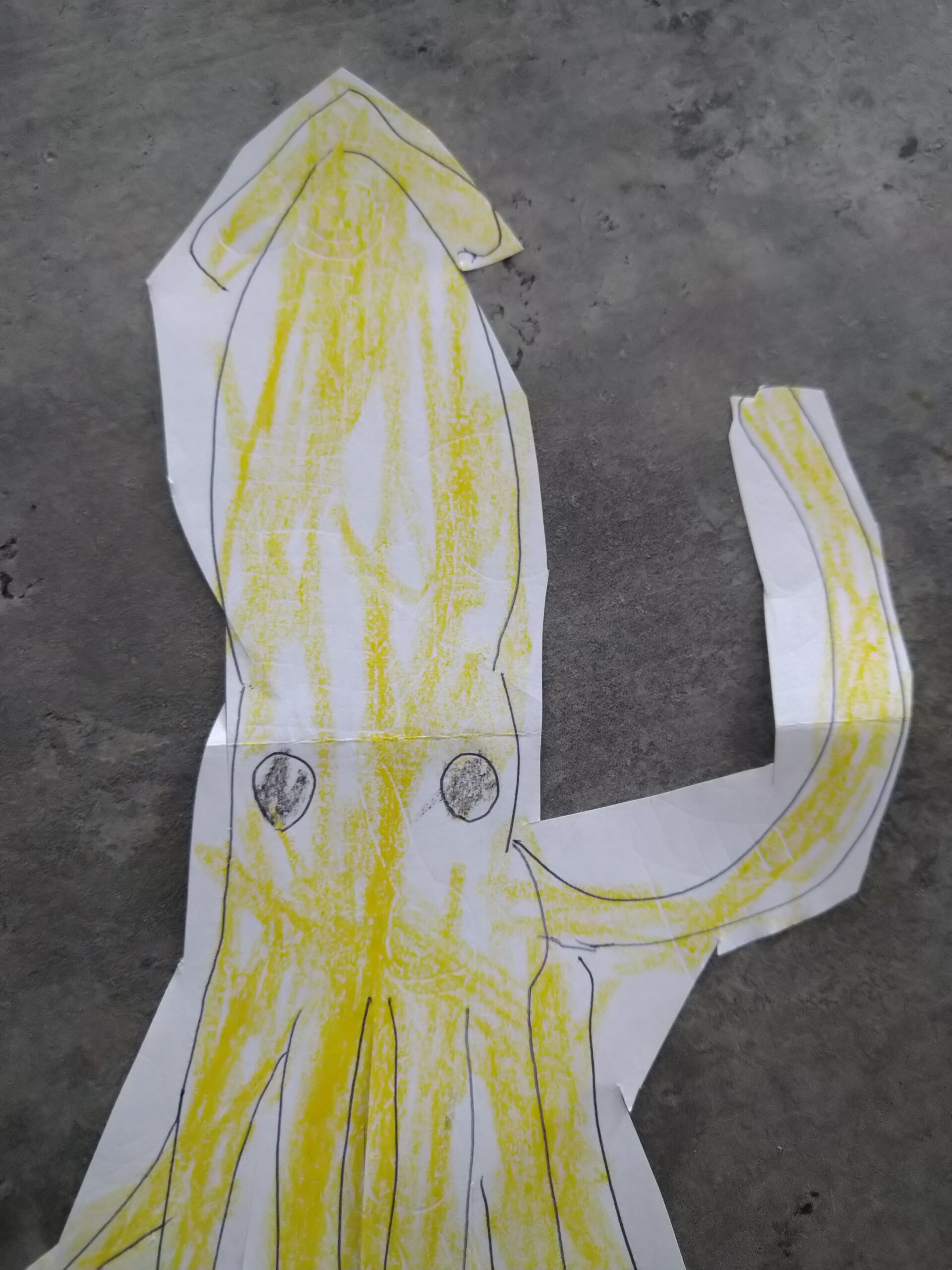
3~4日を目安に消費しよう。

■食卓に出すとき
- 大根おろし・・・お好み
- きざんだこねぎ・・・お好み

積極的に消費していきましょう。
4. 焼きナス
■材料・調味料
- ナス
- 大根
- 醤油
■手順
- ナスはヘタを落として、縦に4つくらいに切る
- 大根は皮をむき、お好みの量をすりおろしておく
- フライパンに油をひいてナスを焼く
- ナスに火が通ったら皿に盛る
- おろし大根と醤油をお好みでをかける
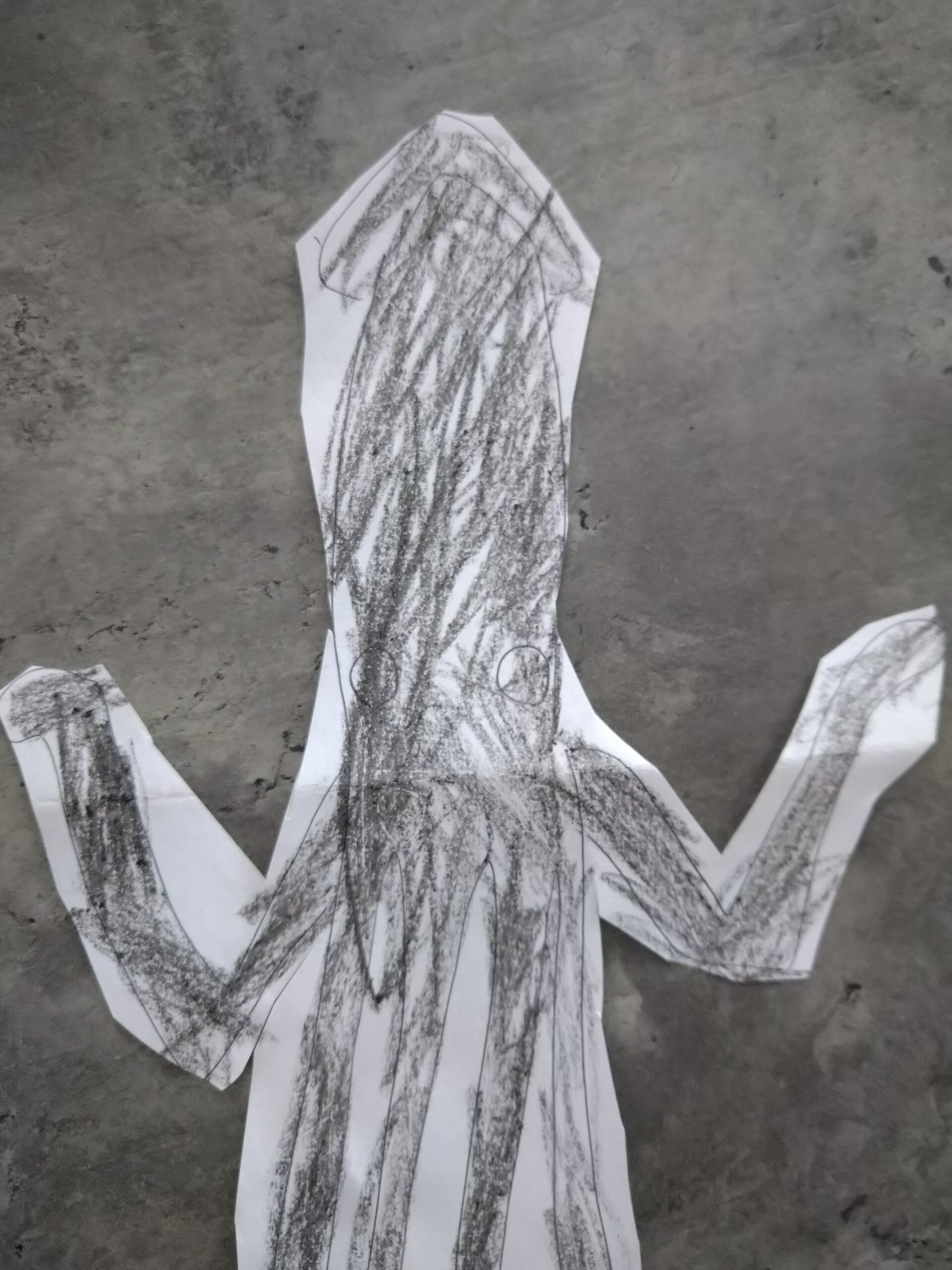
焼いているだけなのにパクパクいっちゃうよ。
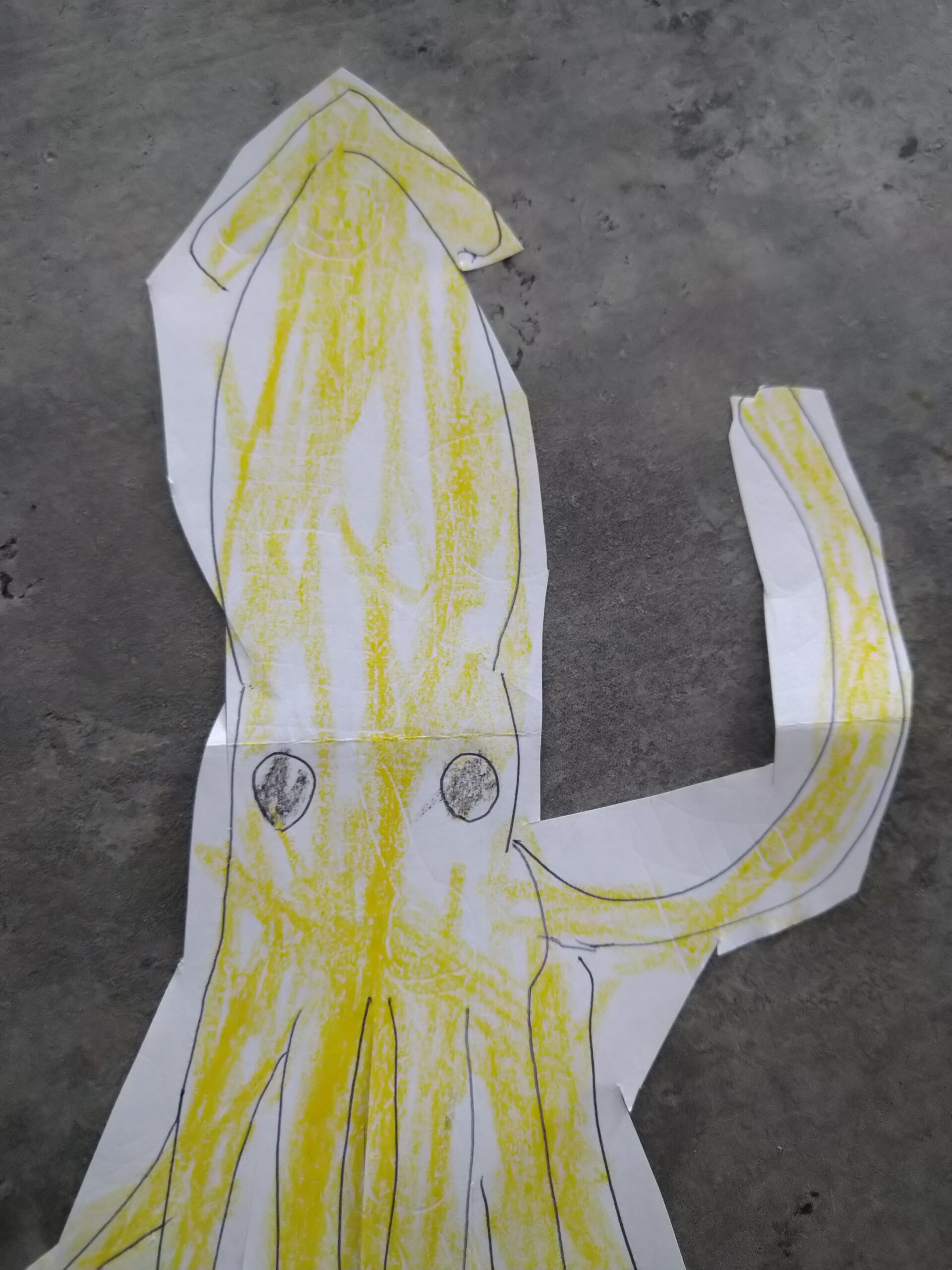
炭で焼いてもおいしいよね~。
5. ナスの天ぷら
野菜の天ぷらといえば、”ナスの天ぷら”は欠かせません。
■材料・調味料
- ナス
- 油
- てんぷら粉
- 塩
- てんつゆ
■手順
- てんぷら粉と水をまぜておく(多少”ダマ”が残る程度)
- なすはヘタを切り落とし、2.5~3㎝の輪切りにする
- 油を170℃ほどに熱する
- バットにキッチンペーパーを引く
- ナスをてんぷらの衣にくぐらせ、熱した鍋に投入
- カラッと揚がったら4のバットに数分乗せる
- 皿に盛りつける
- てんつゆか塩でいただきましょう。
6. 麻婆ナス
■材料・調味料
- ナス
- 麻婆ナスの素
■手順
- 麻婆ナスの素のパッケージの裏に作り方は載っているのでそれを見ましょう。
まとめ
”ナス”ひとつとってもさまざまなレパートリーがあります。
さすが”ジャンルを問わずに使える”野菜と言ったところですね。
■ナスを大量にもらったら!
- 『冷凍保存する』
- 『南蛮びたし』でつくりおき
■茄子の代表レシピ
- 焼きナス
- ナスの天ぷら
- 麻婆ナス
消費しきれない量をもらって困るのはわかりますが、昨今、野菜に限らず食材が高いのも事実。
捨てるのはもったいない、せっかく頂いたわけです。
上手に、カンタンに保存・つくりおきして、少しでも食費を浮かせましょう。



コメント